「もっと感情を出して」
「それ、全然伝わってこない」
演出家や審査員からそんな言葉を投げかけられた経験、ありますか?
僕はあります。
めちゃくちゃあります。
……はじめたての頃ですよ。(念のため、笑)
自分では感情を込めたつもりでも、「棒読みっぽい」「嘘くさい」「なんか浮いてる」って言われて、ああ…またダメか…って落ち込むあの感じ。
演技の世界に飛び込んで最初にぶち当たる壁って、大体この“見え透いた演技”問題です。
でも、この“下手な演技”にはちゃんと理由があります。
そして、その理由がわかれば、抜け出す方法もちゃんとある。
この記事では、初心者がよくハマる「下手に見える演技」の原因と、それを自然な演技に変える5つの実践方法を紹介します。
記事を読み終わるころには、「明日の稽古がちょっと楽しみになる」くらいの前向きな気持ちになっているはずです。
見え透いた下手な演技の原因を理解する

演技が不自然に見えるのには、それなりの“原因”があります。
まずは、何が原因で“見え透いた演技”に見えてしまうのかを、具体的に見ていきましょう。
棒読みになるのは「間」と抑揚を外しているから
セリフを一生懸命覚えて、感情も込めたつもり。
でも、いざ本番で演出家に言われるんです。
「ごめん、それ、棒読みに聞こえる」
「もっと感情込めて」
……え?ウソでしょ? 全力で感情込めたんですけど?
この「観る人」と「演じる人」の“ズレ”は、感情の問題ではなく、技術の問題です。
具体的には、
- 間がない(または一定)
- 抑揚が単調
- 呼吸が止まっている
わかりやすいところで言うと、これらの3点がそろうと、人は“棒読み”と感じます。
感情がこもっていても、間がなくて(または一定)、全部同じトーンで喋ると、「読み上げてるだけ」に聞こえてしまうんですね。
オーバーアクションが嘘っぽさを生む

オーディションで言われたことがあります。
「すごく頑張ってるのはわかる。でも、見ててしんどい」
たしかにその時は、全力の涙、全力の絶望、全力の腕の振り上げ、をやってました。
でも現実には、人はそんなにドラマチックに動かない。
極端な話、「泣くのを我慢する」「絶望している姿を見せないように耐える」のように、必死に自分の感情を抑えようとか、隠そうとする姿に、逆に心打たれることも多いんです。
演技が“大きすぎる”と、それだけでリアリティがなくなります。
「観てもらいたい」気持ちが先行すると、つい動きがオーバーになりがち。
でもそれが、逆に“演じてます感”を際立たせてしまうんです。
目線や呼吸が乱れると不自然さが際立つ
「目が泳いでる」
「呼吸が浅くなって声が浮いてる」
これは、演出家から何度も指摘されましたことがあります。
最初は意味がよくわからなかったけど、映像で自分の演技を見たときに気づいたんです。
目と呼吸って、感情よりも先に“違和感”として伝わるんですね。
緊張してると、視線が定まらなかったり、呼吸が浅くて声が不安定になったりする。
(※もちろん、役柄や状況によってはそう見せた方が良い時もあります)
逆に言えば、目と呼吸を効果的に表現するだけで「演技が落ち着いて見える」んです。
見え透いた下手な演技を自然に変える5つの方法

ここからは、そんな“ズレた演技”を今すぐ自然に変えるための5つの具体策をご紹介します。
① セリフを「丸暗記」せず、「誰かに伝える言葉」にする
セリフは情報じゃない。
「伝えたい気持ち」の形です。
ただ覚えて読むと、必ず“棒読み”になります。
でも、「この人に、こういう気持ちで届けたい」と思って発すると、同じ言葉でも全然違う響きになります。
やってみよう
- 「誰に」伝えてるのかを明確にする
- そのセリフを言う“直前の感情”を想像する
- 自分の言葉に一度変換してからセリフに戻す
例
✕ 「ありがとう(棒)」
〇 「……ありがとう(間を置いて、少し照れながら)」
この“ため”が入るだけで、空気が変わるんです。
② 動きを「胸幅」以内に収めて余計な力を抜く

大きく動く=感情が伝わる、ではありません。
大事なのは「どのタイミングで」「どう動くか」です。
動きは小さくても、ベストなタイミングで、ベストな動きをするとしっかりと伝わります。
むしろ、“動かない演技”のほうが強く届くこともあります。
僕が初めて映像の現場に立ったとき、演出家から言われました。
「動くな。顔も動かすな。目だけで伝えてみて」
……これが、めっちゃ怖かった。
でも、「目は口ほどに物を言う」という言葉のとおり、目だけに集中した演技って、観てる方は引き込まれるんです。
ポイント
- 手や体の動きは「胸の幅」以内に収める
- 感情を“動き”ではなく“声と目”に乗せる
- 動きを抑えることで、呼吸や声が安定する
③ 自分の体験と感情を“声”に乗せる
演技初心者にありがちなのが、「役の感情を想像や憶測だけで作ろうとすること」。
でもそれって、かなりしんどいです。
そこで使えるのが、自分の中にある“似た感情の記憶”。
やってみよう
- セリフと似た経験を軽く思い出す
- そのときの“身体感覚”を少しだけ再現してみる(声のトーン・息の速さ)
- 完全に感情移入する必要はなく、“雰囲気”を持ち込むだけでOK
例
「そんなの、ずるいよ」
→子どものころ、兄弟だけが特別なお菓子をもらって自分には回ってこなかったときの気持ちを思い出して、その“悔しさ”を少し声にのせてみる。
そのようにして、今までに「ずるい」と感じた体験や感情をできるだけたくさん思い出してみてください。
フィクションのセリフと自分のリアルを少しずつ近づけることが、演じるうえで大きな助けになります。
演技が“自分ごと”に近づくと、それだけで自然に見えてきます。
④ 録画で「棒読み・目線・間」を客観的にチェックする

これは勇気いります。
でも、超効きます。
僕も最初は自分の録画を見るのが嫌で仕方なかった。
でも、自分の癖って自分じゃわからない。
チェックポイント
| 項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 棒読み | 声が一本調子じゃないか/感情が浮いてないか |
| 目線 | 目が泳いでないか/一点を見つめすぎてないか |
| 間 | 相手の言葉を“待てて”いるか/言葉の余白があるか |
習慣化のコツ
- 毎日3分の録画練習
- その日の改善ポイントを1つだけ書き出す
- 録画→メモ→次の稽古で意識、をルーティンに
⑤ 日常会話の自然さをそのまま持ち込む
演技が不自然に見える理由のひとつは、「相手との関係性」が曖昧なままセリフを発していることにあります。
たとえば──
- 「なんか今日さ、ちょっとしんどくてさ」
- 「え?マジで?それヤバくない?」
この言葉って、友達だからこそ成立してる話し方ですよね。
これが上司とか先生相手だったら、こんな口調にはならないし、逆にすごく親しい人にまで敬語で話してたら、ちょっと距離を感じたりします。
誰でも、普段は無意識のうちに「相手との関係性」に合わせて、言葉の選び方も、声のトーンも、自然に変えてるんですよね。
つまり、「自然な演技」というのは、感情を出すことよりも前に、「誰を相手に」「どう話すか?」をちゃんとイメージできてるかどうか。
ここが大事なんです。
よくあるのが、「セリフは覚えたけど、誰に対してどんな距離感で喋ってるのかが見えてこない」っていうパターン。
つまり、その人との「関係性に説得力がない」ということ。
これだと、どれだけ感情を込めたつもりでも、どうしても嘘っぽく見えちゃうんですよね。
やってみよう
- セリフを言ってる「相手」をはっきり決める(上司?兄弟?恋人?)
- その人との距離感を、現実の誰かに置き換えてイメージしてみる
- 普段その相手とどう接してるか、どんなテンションで話すか思い出す
- 一度、その“いつもの空気感”でセリフを読んでみる
演技に日常の自然さを持ち込むって、呼吸や声のトーンだけじゃなくて、「人間関係のリアリティ」まで持ち込むことなんです。
役の人物の「日常」が見えると、一気に演技に説得力が生まれます。
「自然な演技を身につけたい」と思ったとき、自分に合った養成所の環境を選ぶこともすごく大事です。
初心者向けにポイントを整理した記事もあるので、よければこちらも参考にしてみてください。
▶︎ 失敗しない俳優養成所の選び方とおすすめ5選【初心者OK】
まとめ:見え透いた下手な演技を直す近道
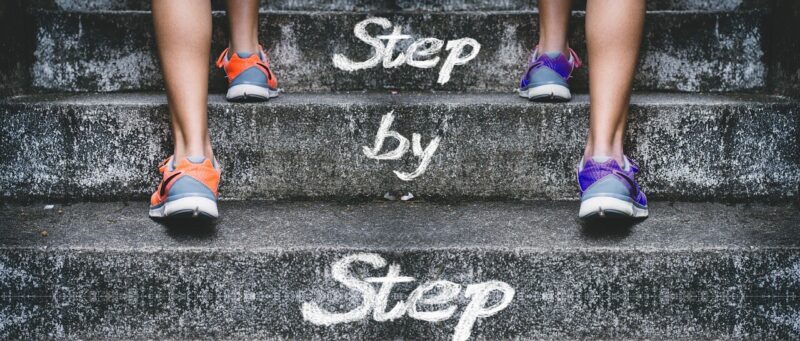
最後に、ここまでの内容をすぐ実践できるステップにまとめます。
今日からできる!自然な演技に変える3ステップ
- 1日3分、セリフを録画して確認する
- そのセリフを“誰に・どんな気持ちで”伝えるか考える
- 実生活の会話を観察して、演技に活かす
「下手って言われた日」から演技は始まる
演技を始めたばかりの頃、毎日のように言われていました。
- 「浮いてる」
- 「感情が伝わらない」
- 「やってることが全部バレてる」
当時は正直、言われるたびに凹んでました。
でも今思うのは——
言ってもらえたからこそ、自分のズレに気づけたんだということ。
誰にも何も言われないままだったら、きっと、自分の“思い込みだけの演技”を何年も続けてたと思います。
演技って、自分を否定されることも多い世界です。
でも、それは「直せるから」「伸びしろがあるから」言ってくれてること。
だから、指摘されても落ち込まないでください。
「これでまた一つ、自分の演技のクオリティが上がるんだ」と、ちゃんと受け止めて、直していく。
その積み重ねが、“ちゃんと伝わる、説得力のある演技”に変えていきます。
明日の稽古、3分だけ録画してみませんか?



